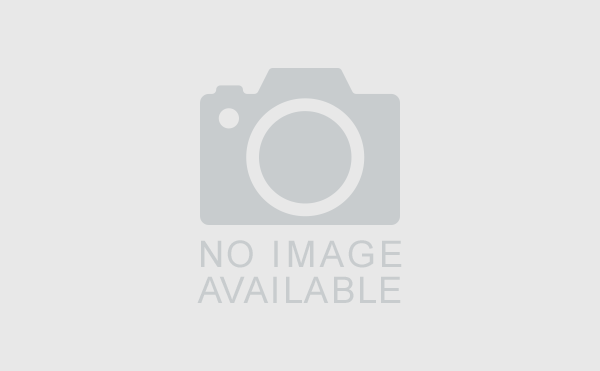1.最終評価の背景と目的
奄美大島生物多様性地域戦略(以下、「本戦略」という)は、生物多様性基本法に基づき、奄美大島の5市町村(奄美大島自然保護協議会)によって2015年3月に策定されました。本戦略は2024年度までの10年間の計画であるため、次の10年間の計画として必要な見直しを実施しています。この見直しに当たって必要な課題を把握するため、本戦略の「行動計画・重点施策」に位置付けられた事業について、この10年間の進捗状況を評価しました。また、これらの事業による取組の成果として、本戦略の「短期目標」として掲げられた10年後(2024年)の奄美大島の姿について達成状況を評価しました。
2.行動計画・重点施策の取組状況評価の概要
行動計画や重点施策の改定に向けた課題を把握するため、地域戦略の「第6章行動計画」に位置付けられた各取組の状況や具体的な進捗内容、課題について、5市町村が整理を行い、基本方針ごとにまとめました。
○基本方針1 生物多様性の保全・管理
島内の野生生物を保護・管理するための取組には、島内全体として大きな進捗が見られました。特に、「既存制度を活用した重要な地域等の指定」、「野生生物交通事故防止対策実施の推進」、「外来種の駆除活動の支援・推進」、「鳥獣被害対策の支援」、「ノネコ対策、ノヤギ対策の強化」などの取組では、奄美大島自然保護協議会や国、県、事業者、住民など様々な主体の参画により取組が進められました。その結果、奄美群島国立公園の指定と世界自然遺産登録という大きな成果も得られました。また、世界遺産地域外も含む取組として、「森林の再生」や「耕作放棄地の解消」、「自然海岸(渚)やサンゴ礁の保全」、「河川・地下水・海域の水質保全」などが既存の計画や制度に基づき進められました。さらに、気候変動対策として、地球温暖化防止実行計画の策定が5市町村全てで進められました。
一方で、レッドデータブック作成、外来種対策、公共事業への配慮など、すでに国や県によって進められている取組や、マングローブ保全や市街地の緑化など、自治体ごとに自然環境条件が異なる取組については、各市町村独自の動きは慎重に検討され、取組状況にはばらつきが見られました。また、国立公園など既存の保護地域以外の、より住民に身近な地域における「重要な地域の指定」や「集落での希少野生生物保全活動の支援」についても、5市町村で世界自然遺産に関する取組を優先する中で、自治体ごとの進捗に差が見られました。
○基本方針2 自然共生社会構築の仕組みづくりと人材育成
主に児童向けの取組として、「給食で地産地消の推進」や「自然体験などの学習機会提供の検討」などが各地で具体的に進められました。これらの取組では、奄美大島自然保護協議会、教育機関、奄美博物館、環境省などと協力し、世界自然遺産の現状や課題、奄美大島の自然環境の保全と継承等について積極的に取り組まれました。また、幅広い対象に向けた「生物多様性保全に係る情報の収集と発信」などの普及啓発活動について、SNSの活用や世界自然遺産推進共同体の協力を通じて実施されました。さらに、「新規の農林水産業就業者の確保・育成」や、山林・海岸等における廃棄物対策など、島内の自然環境と密接に関わる産業における人材育成や体制づくりに関する幅広い取組が進められました。
一方で、生物多様性の保全や活用に専門的な知識や技術を有する「委嘱者等のリストの公表」など地域活動への支援については、住民からの問い合わせに対する人材の紹介などが都度実施されているものの、人材リストの公表や支援制度化については緊急性の観点から慎重に検討されました。また、自然体験活動や学習機会の提供は進められているものの、それを支える教育の担い手の育成は市町村ごとに実施状況に差がありました。さらに、住民の協力を得る必要がある「住民参加による自然調査」については、専門的な知識を要するなど技術的な課題があり、未着手の自治体が多い状況でした。
○基本方針3 生物多様性の持続可能な利用
持続可能な農林漁業に関する取組として、農業分野では「耕作放棄地の解消」に向けた団体の立ち上げや自治体独自の開墾事業、交付金による農地再生の支援、「生物多様性に配慮した特殊病害虫対策」などが5市町村で広く実施されました。林業分野では、「マツクイムシ被害への対応」や「森林の再生」、その他の森林整備計画等に基づいた取組が進められました。漁業分野では、漁業協同組合との連携により「天然漁業資源の保全」が進められました。また、消費の面からも島内資源の持続可能な利用に関する取組が進められ、「食育の推進」や「地産地消」、その他「生物多様性の保全につながる暮らしについての情報提供」などが5市町村で広く取り組まれました。 一方で、「自然遊歩道の整備」など施設整備に関しては、国や県等の事業が既に存在しているため、市町村独自の整備については安全管理や維持管理を含めたコストを考慮し、慎重に検討されました。また、「生物多様性の保全に配慮した商品利用の拡大」、「生態系サービスの持続的な利用の検討」については、島内各地域で受け継がれてきた島の恵みに関する知識の集約などに課題があり、自治体ごとの取組状況にはばらつきがみられました。
3.短期目標の達成状況評価の概要
本戦略の「第4章 基本的事項と目標」では、短期目標(2024年の奄美大島の姿)として「目指すべき姿」を10項目掲げています。それらの達成状況を各種データ(例:世界自然遺産モニタリングの結果など)も参照し、「進捗した成果」と「問題・課題と考えられる事項」を評価しました。
※短期目標の達成状況は本戦略の取組だけでなく、他の関係主体(国・県・大学研究機関・民間等)の各種計画や取組を含む総体的な結果です。
- 奄美群島国立公園の指定や世界自然遺産登録で、森林の生物多様性の劣化は抑制されています。一方、海域ではサンゴの劣化や、ウミガメの上陸・産卵数が減少しています。耕作放棄地やサンゴ礁、マングローブ林等で、劣化・消失した生物多様性を回復・再生する取組が始まっています。
- マングースの根絶やノネコ対策の進展で、野生動物の生息状況が回復しています。希少種の盗採・持ち出し防止対策に努めていますが、その疑いのある事案が毎年確認されています。また、野生動物のロードキルやアマミノクロウサギによる農業被害の急増が、人と自然の共生上で新たな課題となり、関係機関が連携して対策に取り組んでいます。
- マングース防除やノネコ対策が科学的・計画的に進められ、マングースは2024年に根絶が宣言されました。飼い猫条例でネコの適正飼養を進めていますが、放し飼いの屋外ネコが一定程度存在してます。海岸部や山中でノヤギの確認例が増加しています。
- 島民や来訪者の外来種に対する認識が高まり、島民参加の外来種調査や駆除活動も進められています。一方、ソテツシロカイガラムシの侵入で大きな被害が生じており、防除に努めていますが効果的な方法が確立されていません。
- イノシシ等による鳥獣被害対策は捕獲従事者の高齢化が進み、後継者育成が課題です。外来種のノヤギも含め、科学的・計画的な対策検討と体制づくりが求められます。
- 生物多様性に対する島民や来訪者の認知度は非常に高く、群島民の約8割、群島来訪者の約9割が、世界自然遺産として生物多様性の保全上重要な地域と認識しています。
- 生物多様性や自然の恩恵を学べる施設は数・内容とも充実しています。関係機関の連携のもと、児童生徒の自然体験学習や教員研修の機会・教材の提供が進められています。社会人や行政職員が対象の環境文化教育プログラムを鹿児島大学が開講しています。
- 農林水産業の各分野で生物多様性への配慮に取組んでいます。奄美大島で認定された「自然共生サイト」3か所のうち2か所は、農業や水産業と生物多様性や伝統文化の保全の両立を目的としています。伝統野菜等が学校給食やイベント等で活用されていますが、奄美ブランド化や商品利用の拡大が今後の課題です。
- 行政機関、学識経験者、活動団体、民間事業者等が、世界自然遺産の保護管理、希少種保護や外来種対策、拠点施設の管理運営、普及啓などに対し、会議体や協議会の設置、連携協定の締結、実働現場での協力など、役割分担・連携して取り組んでいます。
- エコツーリズムの推進に向けて、エコツアーガイド登録・認定制度、主な利用場所の利用ルール試行等が関係機関の連携のもとで進んでいます。住民生活に配慮した集落散策ガイドも実施されています。持続可能な観光の提供はインターネットで国内外に発信されています。
4.その他
評価結果の詳細は、別添の以下をご参照ください。